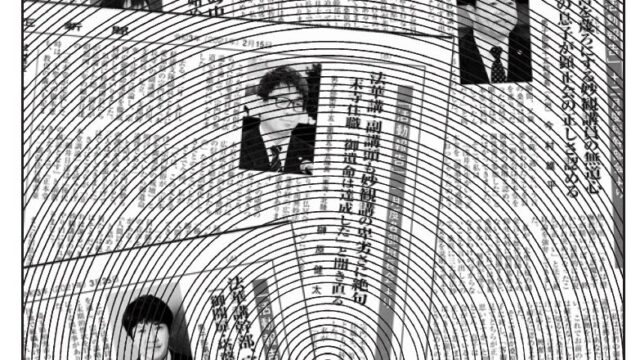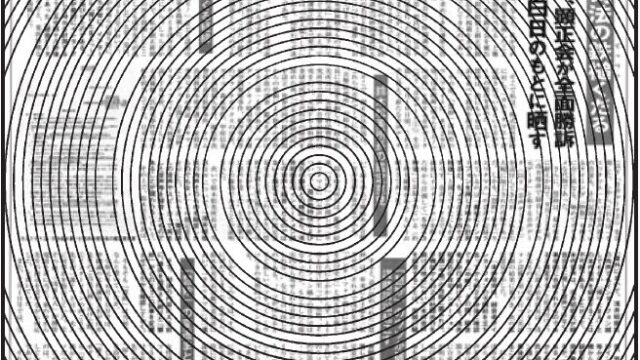「断命は国主のみ」「謗法禁断が本意」というも「謗法が極悪になれば対治を徹底すべき」「仏法破壊の悪人と戦う実力を持て」と
顕正会会長・浅井昭衛は、『立正安国論』に引用される涅槃経の文を解釈する形で、次のような持論を展開している(少々長くなるが引用する)。
「命根断絶で未来の堕地獄を救う」と浅井
「殺生(せっしょう)はなによりの悪事であるが、殺された相手のいかんにより、殺した罪の軽重に差が生ずる。さらに一歩を進めれば、一国社会の安全を害するような極悪人に対しては、これを援助する者は大罪を作り、害する者はかえって社会に対し善行をしたことになる。この理(ことわり)により、今日の社会においても、極悪人に対しては国家は死刑を行っているのである。
いわんや正法を破壊する謗法の行為は、現世には国を亡ぼし未来には万民を永く地獄に堕とさせるゆえ、その罪の大なること深きこと、世間の極悪人に勝ること百千万億倍である。これがわかれば、国主たる者は自らの責務として、これら謗法の者の命根(みょうこん)を断じても、その極悪を止めなければならない。
さて、釈尊が過去世において国王たりし時、謗者の命根を断ったというのも、いつに謗法を禁(とど)めて正法を護持するためであり、また大慈悲のゆえである。
大慈悲のゆえに命を奪うというのはおかしく聞こえるかも知れぬが、よくよく考えれば、謗法者は知らずとはいえ自らの仏種を破壊せんとしているのだ。この自らを殺す非行を命根断絶により救済する。すなわちその色心を断じて慧命(えみょう)を全うさせるのである。またこれ以上の悪業をなすを許さず、命根断絶して未来の堕獄を救うのである。されば殺にも憤怒(ふんぬ)・残忍から出るものと、このように慈悲より出るものの二つがあるを知るべきである。
しかしここで注意しなければならないことがある。それは、このような謗法者に対する命根断絶という行為は、国主・国家権力がなすべきことであって、個人は絶対にしてはならない。ゆえに涅槃経にも、釈尊が過去世において国王であった時の行為として説かれているのである」(『立正安国論謹講』一七八頁)
と。
要するに、謗法者に対しては、国主はその命を奪って悪業を止めるべきで、それはかえって善行になり、殺される側にとっても救済になる、というのである。
ここまで読んだときに、過去に、これと酷似(こくじ)した論理を説いた宗教指導者があったことを思い出す。それは、オウム真理教の麻原彰晃である。
麻原も「殺害で相手を堕地獄から救う」と
麻原は
「例えば、Aさんという人がいて、Aさんは生まれて功徳を積んでいたが、慢が生じてきて、この後、悪業を積み、寿命尽きるころには地獄に堕ちるほどの悪業を積んで死んでしまうだろうという条件があったとしましょう。このAさんを、成就者が殺したら、Aさんは天界へ生まれ変わる。(中略)生かしておくと悪業を積み、地獄へ堕ちてしまう。ここで、例えば生命を絶たせた方がいいんだと考え、ポアさせた。(中略)人間的な客観的な見方をするならば、これは殺生です。しかし、ヴァジラヤーナの考え方が背景にあるならば、これは立派なポアです。
そして、智慧ある人─ここで大切なのは智慧なんだよ。─智慧ある人がこの現象を見るならば、この殺された人、殺した人、共に利益を得たと見ます。ところが、智慧のない人、凡夫の状態でこれを見たならば『あの人は殺人者』と見ます」(平成元年九月二十四日・オウム真理教世田谷道場にて)
と述べている。
これはすなわち、オウムの教えに従わない者は、それによって悪業を積み重ね、やがて地獄に堕ちるので、それらの人物が地獄に堕ちる前に、「成就者」がそれらの人物を殺せば、殺された人物は地獄に堕ちずにすむし、殺した「成就者」の方は、殺生の罪障を背負うどころか、かえって功徳を積むことができる、という考えである(これを麻原らは「ポア」と呼んでいた)。
そして、麻原率いるオウム真理教は、平成元年の男性信者殺害を手始めに、同年十一月の坂本弁護士一家殺害事件、平成六年六月の松本サリン事件、平成七年二月の公証人役場事務長逮捕監禁致死事件、そして同年三月二十日の地下鉄サリン事件等々、凄惨(せいさん)極まる事件を次々と起こしていったのであるが、信者らが平然と、このような世にも恐ろしい事件を起こしていったその背景には、麻原の「ポア」思想があったのである。
麻原は、こうした断命(つまり殺害)を行なう者は「成就者」「智慧ある人」である、と言い、浅井は「国主」「国家権力」に限る、と言うが、つまるところ、教えに従わない者は殺害した方が「善行」となり「功徳」となる、とする点では軌を一にしている、といえよう。
経文を曲解して「武器を持って戦え」!?
さらに浅井は、武力による実力行使について、次のように主張する。
「もし仏法が悪人によって破壊されんとする時に、おのが品行方正だけに安住し、枝葉(しよう)の儀式・形式などにとらわれている者は不忠の弟子である。よって仏法守護に立つ者は、五戒とか威儀の末節にこだわることなく、ただ不惜身命の護法心だけを奮い起こし、仏法を破壊する者と戦うべし、と仰せられるのである。
『刀剣・弓箭(きゅうせん)・鉾槊(むさく)』とは武器である。要するに、仏法破壊の悪人に対し、仏法を守護するだけの実力を持て、との意である。実力なき者は護法をなし得ない。これをなし得なければ五戒を身に持っていても持戒とはいわない。ただ実力を以って身命も惜しまず正法を守る者を、始めて持戒の者という。この厳しい戒めは、仏法まさに滅せんとする時、仏法を守ることがいかに大切なるかを御教示下されたものである」(同書一八六頁)
と。
つまり、護法のために〝実力行使〟ができない者は信者ではない、というのである。
浅井が解釈している涅槃経の元意は、次下までよく読んでみれば、謗法者が武器を持って正法の僧を殺害せんとする時には、防衛のための武器使用を許すが相手の命を奪ってはならない、というものなのだが、浅井はそこをボカシて、仏法を破る悪人には武力による実力行使をもって退治しなくてはならない、という考えを強調しているのである。
これを読んだ会員が、仏法を破る者=仏法の教義解釈を曲げる者(むろん彼らの目から見て)=実力行使の対象となる悪人、と理解するとしたら、それはそう理解した者の失(とが)か、そう理解するようにミスリード(誤導)した者の失か、その答えは明らかであろう。
浅井はまったく危険思想を捨てていない!
さて、浅井が講じる『立正安国論』中で、日蓮大聖人は
「釈迦の以前の仏教は其(そ)の罪を斬ると雖も、能仁(のうにん)の以後の経説(きょうせつ)は則ち其の施を止む」(御書二四八頁)
と仰せられ、釈尊の過去世における修行中には断命等の行為があったが、釈尊が仏法を説いた以後は(悪人をも救う道が説かれたので)断命を行なわず、布施を停止することをもって邪宗謗法をなくすのである、と断命を禁じておられる。
この金言を全く無視するわけにいかない浅井は、いちおう
「釈尊以前においては命を断ずることが説かれているが、釈尊以後の時代・社会においては、施を断つことを以って断命に代えるのである。
これは謗法者の命を断ずること自体が本意ではなく、あくまでも謗法を禁断することがその目的であるからである」(同書一七九頁)
と述べている。これで浅井が、断命とか武力行使という危険思想を否定した、と言えるのか、というと、それは否であろう。何故ならば浅井は、その言葉に続けて、
「ただし大聖人の御振舞いを拝するに、この立正安国論を以って第一回の諫暁をなされたのち、良観等の謗法の法師は、自非を悔(く)いるどころか、かえって主師親の三徳たる大聖人を国主に讒言(ざんげん)して殺害せしめんとした。このように謗法が極悪になり、その罪禍により国まさに亡びんとするに至れば、謗法対治もまた徹底せねば国は持たない。よって大聖人は文永八年の第二回目の諫暁の時、平左衛門に向って〝良観等の頸を刎ねよ〟と強諫(ごうかん)し給うたのである」(同書一七九頁)
「将来、日本国の王法がこの守護付属にめざめ、国主も大臣も全国民も、正法守護に不惜身命の誓いをなす時が必ずくる」(同書一八五頁)
等と述べ、先々に謗法が濃くなって極悪になれば、謗法者の断命をせねば国が持たない、その時は、国主たる天皇はじめ全国民が命を賭けて戦わねばならない、としている(むろん、これは浅井の勝手な解釈であるが)。つまり、将来において断命や武力行使を行なうべき時がくる、ということを示唆しているのである。
しかして、顕正会のこれまでの来し方を振り返れば、こうした浅井昭衛の危険思想の影響としか思えない、会員の暴走、脅迫、集団暴行等が、すでに幾度も発生している(その事例は紙面の関係で挙げないが)。
顕正会員は、文字どおりの浅い教学に誤導され、危険な道へと引き込まれていたことに気付くべきである。そして我々も、かかる顕正会から、一人でも多くの会員を救い出すため、慈悲の折伏行に励まねばならない。
(『慧妙』令和2年6月16日号より転載)